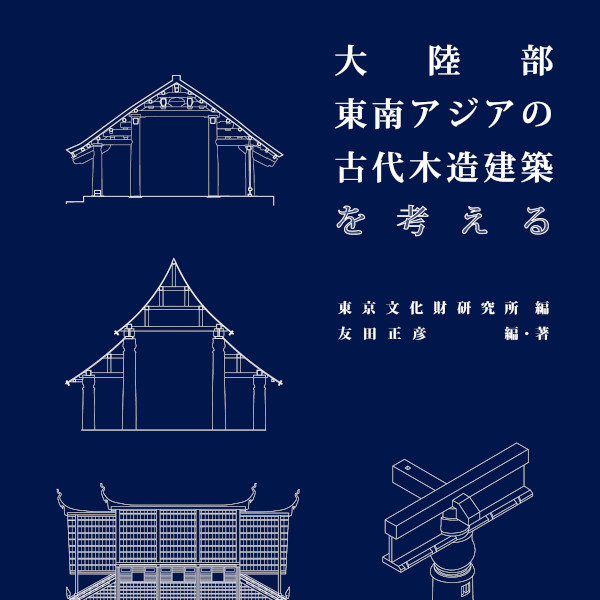風と水を扱う技術

イランの国土の大部分は乾燥気候に属しています。年間を通して非常に雨が少ないこの地で、動植物が生き延びることは容易ではありません。しかし、一見、不毛の地のようにみえるこの場所でも、はるか昔から人々は土を耕し、麦を育て、家畜を飼い、日々の暮らしを営んできました。そこでは、厳しい気候条件ゆえに発達した、地域特有の建築・土木技術をみることができます。
乾燥した平地の村では、数十kmも遠方の山から、カナートと呼ばれる地下水路で水を引きます。村にはアブ・アンバールと呼ばれる大きなドームをもつ貯水槽があり、ここから誰でも水を飲むことができます。サッカベと呼ばれる共同の水場は、男女別に分かれており、人々が水浴びをしたり、洗濯をしたりします。サッカベから流れ出た水は、タルヘと呼ばれる溜池に溜められます。ここでは、羊やヤギ達が立ち寄って喉を潤します。カナートから流れ出る豊富な水は、さらに水下の農地に配分され、麦や野菜を育みます。

限られた自然資源を巧みに扱う技術は、水資源に関わるものだけではありません。イランの人々は、風の性質を理解し、それを扱う術に長けていました。
イラン東部からアフガニスタン西部にかけた地域では、強力な季節風を利用し、古くから風車を用いて製粉や揚水を行ってきました。風車といえば、オランダの風車を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、イランの風車はこれとは異なり、垂直の車軸でくるくると回ります。この垂直車軸をもつ回転羽根の真下に製粉場があり、回転羽根から生まれた動力が、そのまま直に伝わって石臼を回転させるという仕組みです。風車をつくる主な材料は、日干し煉瓦と木材です。時代や地域によっては、葦の束や麻布、動物の皮の紐、鋳鉄を用いることもあります。ほぼ土に還る材料でつくられた、単純な仕組みをもつ原始的な動力装置といえるでしょう。『ペルシアの伝統技術』を著したハンス・E・ヴルフは、1963年にネーフの町で50基の風車が稼働していたことを記録しています。このような原始的な風車がいくつも並び立ち、莫大なエネルギーを生み出す巨大装置となって回転している様は、どんなに壮観だったことでしょうか。
この地で、風たちは名前をもっています。「120日の風」「黒い風」など、季節の風につけられた名前は、土地の人々と風との間にある物語を感じさせます。風が吹いてくる遠くの山並の切れ目を「風の門」と呼ぶ地域もあります。こうしたことからも、土地の人々が風を理解し、その動きをよく読んでいたことがわかるのです。

これらの歴史的な風車群は、現在ほとんど廃墟化した遺構のまま保存されており、実際に稼働できるものはわずかしか残っていません。けれども、これは廃れかけた技術ではなく、未来の技術でもあるという確信を、私はなんとなくもっています。自然が生み出すエネルギーで人間生活を成り立たせる技術が、必ずしも高度なものである必要はなく、既に私たちの周りに在ることに可能性を感じているのです。
淺田なつみ(ASADA Natsumi)
トップ画像:ナシュティファンの風車群