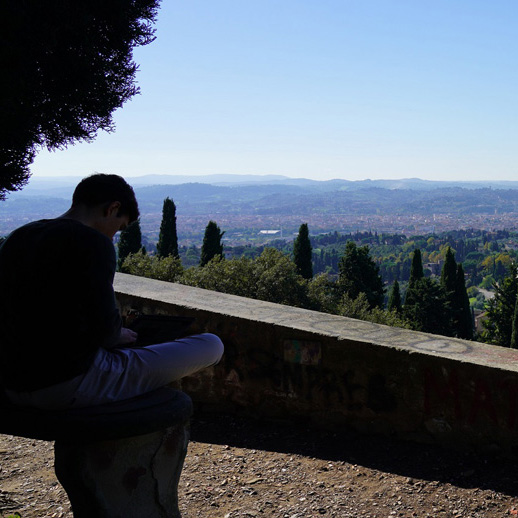「瀟湘八景」から見る異文化受容と再創造

現在、私たちが「文化遺産」と呼んでいるもののうちに、他の文化との接触を経ることなく、完全に独自に誕生したものはほとんどないと言っても過言ではありません。文化は常に他の文化と交わり、影響を受け合いながら、新たな価値や形を生み出していくものです。私が学んでいる美術史の分野においても、人々や物の移動がその背景に深く関わっており、絶え間ない交流と受容のプロセスを通じて、多くの作品が生まれてきました。
私は、日本美術における他文化に対する卓越した「受容力」と「再創作力」に特に強い関心を抱いており、なかでも、中国の絵画のテーマが日本でどのように受け入れられたのかに興味を持っています。今回はその一例として、「瀟湘八景」に焦点を当ててご紹介します。
皆さんは「瀟湘八景」という言葉をご存じでしょうか?もし耳にしたことがなくても、「近江八景」(滋賀県)や「金沢八景」(横浜市金沢区)といった名称には馴染みがあるかもしれません。実は、日本全国には200件以上の「○○八景」が存在しており、その起源を辿ると、中国の「瀟湘八景」へと行き着くのです。
「瀟湘八景」とは、平沙雁落、遠浦帰帆、山市晴嵐、江天暮雪、洞庭秋月、瀟湘夜雨、煙寺晩鐘、漁村夕照という八景をさします。この画題は13世紀に日本に伝来し、15~16世紀には瀟湘八景をテーマとした絵画が数多く制作され、大流行していたことが文献や遺品から確認されています。「瀟湘」という言葉は従来、「瀟水」と「湘江」の二つの川を指すと解釈されてきましたが、実際には「清らかな湘江」を本意としており、瀟湘八景は現在の湖南省の南から北へ、洞庭湖に注ぐ湘江流域全体を指すべきであることが近年の研究により確認されています 。
また、「瀟湘八景」という明確なタイトルが付けられていなくても、「山水図」や「四季山水図」など日本の山水画にはしばしば「八景」のモチーフが描かれています。
その一例として、雪舟の弟子と伝えられる楊月(ようげつ)の「四季山水図屏風」を見てみましょう。

[出典:ColBase]
この屏風は六曲一双で構成されており、右から左へと移り変わる四季の風景と、その中で営まれる人々の多彩な活動が描かれています。右隻(図1)には春と夏の景観が広がり、向かって右から第1扇には、山道を歩む人物が描かれており、彼らの先には、山間に広がる賑やかな市場の光景が見て取れます。これは「山市晴嵐」を表現しており、春の暖かな風を感じさせます。第4扇には、風雨に打たれて枝を垂れた柳がしっとりと描かれており、これは「瀟湘夜雨」の情景を表現しています。また、第4扇と第5扇の近景には、浜辺に停められた漁舟と干し網が描かれており、そこには「漁村夕照」の情景が浮かび上がります。第5扇と第6扇には、山道を歩む僧侶らしき人物とその従者が見られ、その行先には山中に広がる建物群が描かれ、穏やかな夕暮れに響く「煙寺晩鐘」が感じられます。

[出典:ColBase]
左隻(図2)には秋と冬の風景が描かれ、向かって右から第2扇の上部には満月が浮かび上がり、これが「洞庭秋月」を象徴しています。その左下方、第3扇には水面に漂う帆舟が描かれ、これは「遠浦帰帆」を表現しています。さらに左には小さく描かれた雁の列があり、秋の静けさと「平砂落雁」を表しています。そして第4扇から第6扇には雪に覆われた屋根や山々が描かれ、「江天暮雪」の厳かな情景が表現されています。
このように、瀟湘八景は一見すると特別な意味を持たない風景の中に巧みに組み込まれています。当時の鑑賞者にとっては非常に馴染み深いものであったでしょうが、現代の私たちにとっては、まるで隠された「コード」のように感じられます。これらの「コード」を読み解くことで、水墨山水画の鑑賞がより深い楽しみへと変わるでしょう。
一方、本場の中国においては、瀟湘八景は水面が広がる横長の構図の山水画の典型的なテーマとされており、ほとんどの作品は長巻形式の小画面で表現されています。また、季節に関しては、「平沙落雁」、「洞庭秋月」、「江天暮雪」の三景は秋冬の景色を示していることがわかりますが、他の五つの景色は特定の季節と結びついていません。しかし、日本における瀟湘八景図は、より大きな画面に描かれることが多く、屏風や障壁画という形式を通じて、視覚的なインパクトを持つ作品へと発展しました。さらに、これらの大画面においては、八景を四季の流れに合わせて配置した作例が多く見られます。このような構成は、中国絵画の単なる模倣ではなく、日本の文化的背景や美意識を反映させた再創作の結果であるといえましょう。
瀟湘八景に見られる異文化の受容は、単なる模倣ではなく、他文化を自らの文化に溶け込ませ、独自の形で再構築する過程の一例です。このようなプロセスこそが、文化の交流と発展を示す重要な事例といえるでしょう。
もし中世の水墨山水画を目にする機会があれば、ぜひ「八景探し」を楽しんでみてください。隠されたモチーフを見つけることで、作品への理解がより一層深まるのではないでしょうか。
武 瀟瀟(WU Xiaoxiao)
トップ画像:瀟湘臥遊図巻 部分 南宋時代・12世紀 李氏筆 東京国立博物館 出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)