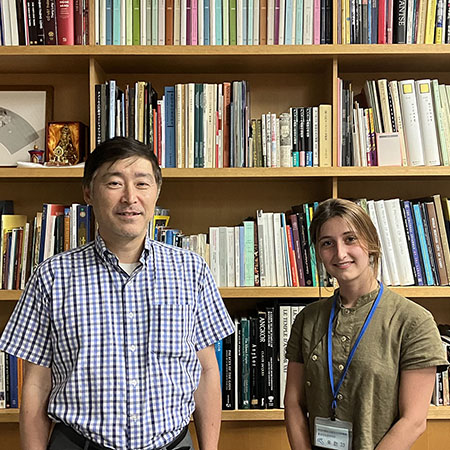作品の価値を未来へつなぐための保存修復倫理

はじめに—ものに手が加えられることについて
ニュースを見ていると、海外の古い教会にある絵画が以前とまったく異なる外見へと描き換えられてしまった事件が時折流れてきます。環境活動家が博物館の作品をターゲットにしたというニュースも記憶に新しく残っています。これらの出来事は、人の手による物理的な介入というものは私たちが作品に対して抱く感情を強くゆさぶるということを改めて思い起こさせます。介入によって脅かされているのは、あるいは作品の価値だともいえるでしょう。芸術的、美的、歴史的、学術的、個人が抱く思い入れや、集団のアイデンティティを生み出す場としての役割、儀礼的機能、そして金銭的な—そういった多様な価値です。
介入という点に着目すれば、どんな修復処置も介入ですから、作品を修復するうえでは、物質的な影響と合わせて価値への配慮も欠かせません。欧米諸国の保存学会が定める現行の職業倫理規程には、修復家の職業責任について以下のような記述があります:文化遺産の価値に敬意を払うこと、自らの技術とその限界を理解したうえで職務に当たること。そしてこうした認識をふまえて、現在と将来世代のために文化遺産を保護する社会的責任を担うこと。
作品分野の垣根を超えて倫理的なふるまいをするための原則のひとつに、「最小限の介入」があります。
「最小限の介入」原則
欧米を中心とした近現代の保存修復は、不適切な介入をどのように未然に防ぐかを動機として発展してきた側面があります。科学的な観察に基づいて行われた修復処置であっても、時が経つうちに、当時では予想しえなかった劣化が急速に顕在化するケースもあります。そこで、将来的な影響をできるだけ少なくする方法が望ましいと考えられるようになりました。同時に、再処置できる余地を残しておくことも肝要です。このように、作品に入れる手をなるべく減らすという方向性は、保存修復とは時代を超えて作品に何かしらの変化を与える行為だという反省をふまえて生まれてきました。
「最小限の介入」と絵画修復の技術発展
最小限の介入原則は、実際に修復技術の発展にも関わってきました。たとえば油絵のキャンバスが破れている時、古典的には、裏打ち(キャンバス裏面全体に別の布を貼りつけ、木枠に張り込んで構造を強化する手法)や、破れた箇所に裏からパッチを当てる方法がとられてきました。しかしこうした方法は、貼りつけ時にかかる圧力や異なる布同士の収縮差、接着剤の経年劣化などによって、作品自体を傷める要因ともなっていました。裏打ちが引き起こす保存上の問題は、1974年にロンドンのグリニッジで行われた国際会議で広く共有されました。
1980年代、ドイツの修復家ウィンフリード・ハイバー博士が、かけはぎという、介入度合いのより低い技術を考案しました。かけはぎは、破れた箇所の裏面に垂直に糸を渡して少量の接着剤で留める手法で、考案後すぐに欧米を中心に広まりました。現在では使われる材料も増え、膠や小麦デンプン糊のような天然の接着剤をはじめ、パウダーやシート状の合成接着剤など、個別の作品に応じて適合性の高い材料が選択されています。
ただ、このような部分的な介入処置にも難点はあります。作品の素材や損傷状態、展示環境によっては、補強の強度が不十分で、あとあと破れが再発してしまうおそれがあります。そのため、かけはぎはあくまで応急処置でしかないと考える修復家もいます。
とはいえ、かけはぎの登場以降、裏打ちが行われる頻度は少なくなりました。こんにちでは部分的な破れのみのために行われることはほとんどないうえ、裏打ちは最小限の介入の原則に反するという意見も散見されます。それでも裏打ちは依然として作品補強のために不可欠な技術です。この修復方法を、作品の構造を変える「大きな」介入であることを理由に、原則にとっての例外と位置付けるべきでしょうか。それとも、最小限の介入自体の意味を問い直すべきでしょうか?
何に対しての最小で、何のための介入か
そもそも最小限とは相対的なものでしかありません。かけはぎも、あくまで裏打ちよりも介入が少ないということにすぎません。とどのつまり、物質的な最小限の介入の行きつく先とは、一切の介入を認めないことになってしまいます。
ここで注目したいのは、英国保存学会(Icon)の倫理ガイダンスで示されている「保存修復は、関係者間で合意した目的を達成するため、可能な限り最も少ない方法を用いて、適切で持続可能かつ効果的に行う(訳筆者)」という文面です[1]。さらにオーストラリア文化財保存学会(AICCM)の倫理規程では、restorationは「最低限の手法で行われる、文化財の解釈を豊かにするための処置(訳同上)」と定義されています[2]。
つまり、最小限の介入の原則を修復方針に掲げることは、物質の介入度合いを減らすことのみを意味しません。それぞれの修復のゴール、すなわち作品のどの価値を保存しようとしているのかを示して、人々の文化的豊かさを守ろうとする態度が含まれているのです。
絵画でいえば、鑑賞や礼拝などによって喚起される価値があります。裏打ちとは、そうした用途に応じて必要な構造的強度を作品に与える選択のひとつです。ですから、当の作品における価値の保存を目的とする限りは、裏打ちも最小限の介入の態度に倣うものと認めてもよいように思われます。むしろ非介入によって作品の劣化が進み、従来認められていたはずの価値が失われるとすれば、かえって文化遺産保護としては不適切といえるでしょう。
多様な人々、多様な文化遺産、多様な修復
修復は作品の物質的な部分へのアプローチを通じて、今見出されている価値と、ひいてはこの先の人々が見出す価値へ、さまざまな影響を与えます。こう考えると、最小限の介入は、物質的な制限によって、価値の可能性を未来へつないでいくためのひとつの保存のありかたを示しているとも考えられます。
現代社会を生きる私たちにとって、多様性を認識し合うことが共通課題であることは疑うべくもありません。文化遺産が多様であると同時に、それを保存するアプローチもさまざまです。作品への敬意があっても、介入の是非について複数人で意見が分かれることも少なくありません。また価値を見定める方法や、その議論をどのように技術的問題へとつなげていくかは、依然としてケースバイケースな課題となるでしょう。しかしだからこそ、修復の目的や社会的役割をよりよく理解するために、最小限の介入原則をはじめとする修復倫理の課題に取り組むことには意義があると考えています。
大川柚佳
トップ画像:(左)かけはぎの様子:作品裏面に、糸を取り付けたトレッカーという黒い補助具を木枠に取り付け、破れに垂直に糸を張る。重しをして破れの口を閉じながら、接着剤と熱を加えて破れ個所に糸を1本ずつ接着する。(右)かけはぎをしたキャンバス裏面の様子:縦方向の破れに対し垂直になるように同系色の糸を接着する。この場合は破れが大きく広がっていなかったため、トレッカーは使用していない。
[1] Icon [Institute of Conservation] 2020. Icon Ethical Guidance. [2] AICCM [Australian Institute for the Conservation of Cultural Material] 2002. Code of Ethics and Code of Practice.