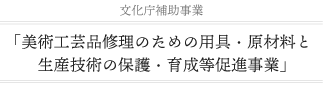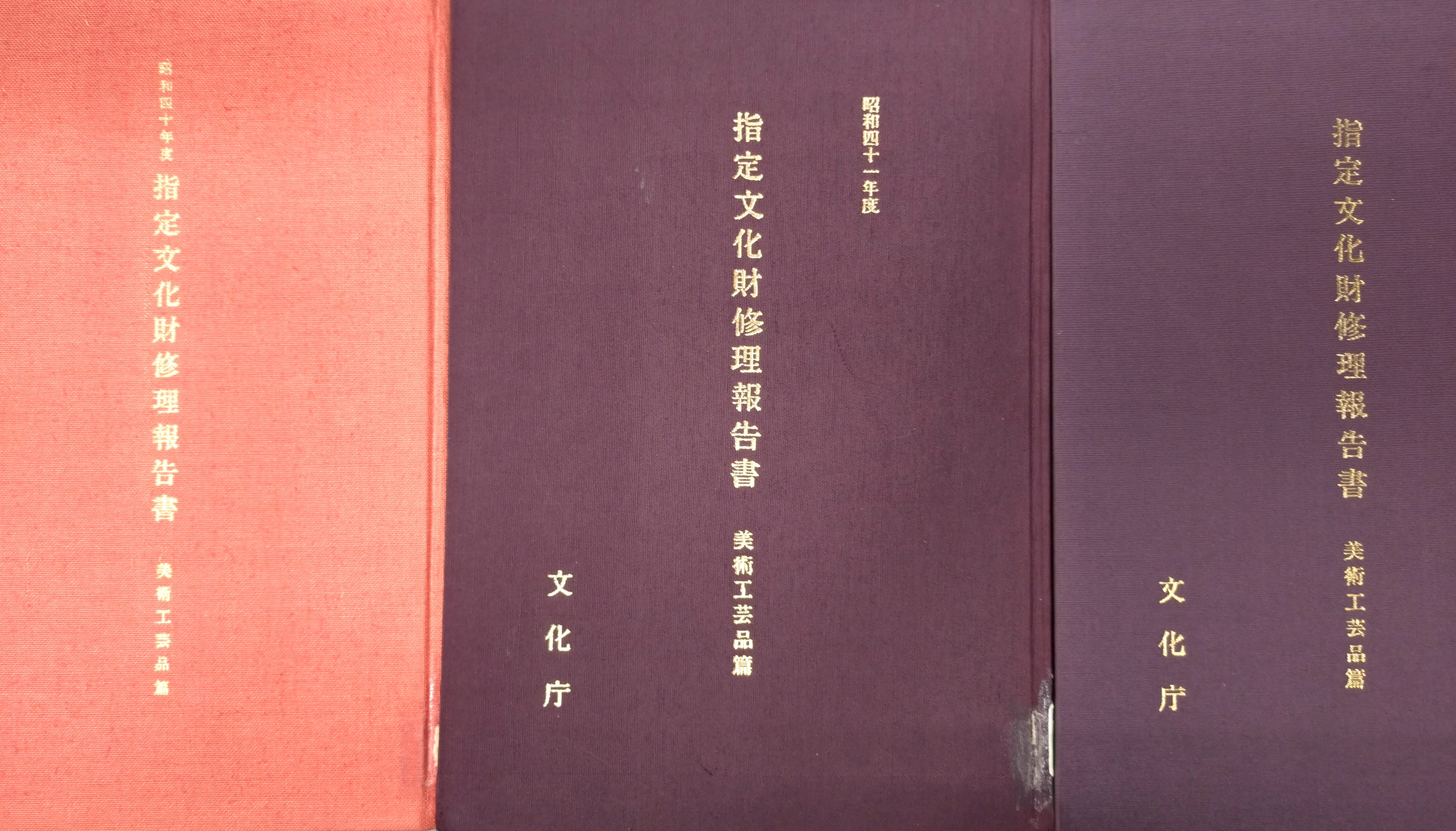本データベースについて
東京文化財研究所では、文部科学省が令和4年度から推進する「文化財の匠プロジェクト」の一環として、文化庁補助事業「美術工芸品修理のための用具・原材料と生産技術の保護・育成等促進事業」を受託し、過去の文化財修理記録(美術工芸品分野)のデータベース化をすすめています。
文化財の修理記録には、その文化財をいつ、誰が、どのように修理・修復したかという情報が集約されています。修理記録は、作品の状態、材料、構造などにかかわる情報の次世代への継承を可能にするのみならず、文化財の管理や未来の修理にとっても重要な情報源となります。
これまでに、文化庁や修理施設のある国立博物館、全国の修理工房、その他の関連組織が修理報告書を刊行してきました。東京文化財研究所でも、在外日本古美術品保存修復協力事業で修復を行った作品のリストをウェブ公開しているほか、修復報告書(刊行物、日本語・英語併記)の全文をリポジトリ公開しています。
このような背景のもと、当プロジェクトでは、以下を目標に、国指定文化財(美術工芸品)の修理記録データベースの試作版を公開いたします。文化財(美術工芸品)修理記録に関するリサーチ・ガイドとしてお使いいただけましたら幸いです(データは2024年度末以降、順次追加予定)。
修理の内容に関しては、文化庁、各博物館等に直接問い合わせください。
- 国指定文化財の修理関連記録(図書や修理報告書等)の広範な収集と目録化・デジタル化
- 公的資金助成を受けた、国指定文化財以外の修理記録(地方指定文化財、在外日本古美術品保存修復協力事業等)の収集と情報集約
- 美術工芸品修理に必要な用具・原材料のデータベース化と調査記録のアーカイブ化
- 上記1から3を統合した総合データベースの構築
凡例
- 国指定文化財(美術工芸品)を対象に、刊行物に収録された過去の修理記録にかかわる基礎的データを文化財単位で集めました。データは現在収集中であり、刊行物収録情報すべてが網羅されているとは限りません。
- 「文化財から探す」と「修理記録から探す」は同一の詳細ページにリンクしています。
- 各文化財の名称ならびに基礎情報には、「国指定文化財等データベース」(文化庁)のデータを用いました。なお現在、独立行政法人となっている国立博物館・文化財研究所等の収蔵品については、所有者が「国」と表記されている場合があります。
- 国指定文化財等データベースの情報と対応ができない文化財の名称は、原典記載のままとしています。なお、原表記を尊重するという観点から、原則として刊行物掲載時の文化財名称も併記しています。
- 修理施工者(工房等)の名称は、原典記載のままとしています。そのため、同一の修理施工者でも、異なった表記となっている場合があります。
- 修理期間は西暦を優先し、原表記が和暦の場合は西暦に変換して収録しました。また、原典に単年度・複数年度事業に関する記述がある場合は、その内容を丸括弧内に転記しました[1996 (単年度)、1990~1996 (7年度継続事業)など]。
- 修理記録数は刊行物への掲載回数であり、修理の回数ではありません。
- 原典に修理内容の記載がある場合は、詳細ページの修理概要欄を「有」、ない場合は「無」としました。
- 漢字は原則として現行通用の漢字を使用しており、明らかな誤字・脱字については修正または軽微な情報の追加を行っている場合があります。
「修理関係刊行物」
- 本データベース所収データの典拠となった刊行物の一覧です。
ご利用にあたって
- 原典をご覧になりたい方は、資料所蔵のある図書館をご利用ください。
- コンテンツの利用にあたっては関係者やコミュニティに配慮するようお願いします。
- 利用者がこの検索システムを使用することによって発生した不利益・損害等に関して、当研究所は一切の責任を負いません。
- URLは予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
- 動作確認は最新版のChrome、Microsoft Edge、Firefoxで行っています。
- 本データベースについてのご意見、お問合せは「info_tobunken@nich.go.jp」までお寄せください。
更新履歴
- 今後、更新についてはトップページで告知いたします。
- 2025年06月27日 更新(文化財数:4,068件 記録数:9,062件)詳細ページに「ふりがな」「修理年表」を追加
- 2025年05月30日 更新(文化財数:3,929件 記録数:8,819件)
- 2025年04月30日 詳細ページに「修理歴」項目を追加
- 2025年03月31日 公開(文化財数:3,192件 記録数:6,389件)
統括:江村知子
データ・目録担当:田良島哲(監修)、片倉峻平、山永尚美、安原大熙、井上いぶき
データベース構築:小山田智寛