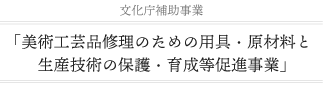本サイトについて
美術工芸品修理において必要とされる用具や材料の今後の供給が危ぶまれています。近年、美術工芸品修理技術を身に付けても生業として成り立たず、従事者が極めて減少しているため、後継者がいない製造業も多く、今後の供給確保が困難な状況に陥っています。東京文化財研究所では、文部科学省が令和4年度から推進する「文化財の匠プロジェクト」の一環である文化庁補助事業「美術工芸品修理のための用具・原材料と生産技術の保護・育成等促進事業」を受託し、これまで行ってきた美術工芸品保存修理に関する情報のアーカイブ化を行うとともに、製造業・生産者の支援と、関係周辺自治体等への理解を高めるため、これらの用具材料に関する記録とその科学的裏付け調査をしつつ、人材育成・情報発信等の協力を行います。本ページでは、これまでに本事業で行った調査・研究の成果について公開いたします。
- 「文化財(美術工芸品)の修理記録データベース」の更新(データの追加)
- 調査実績、業務実績に関する資料等を更新しました。
- 「文化財(美術工芸品)の修理記録データベース」の更新(データの追加)
- 「文化財(美術工芸品)の修理記録データベース」の更新(データの追加)
記録映像
美術工芸品修理のためには用具や原材料の安定的な確保が必要です。しかしこうした用具や原材料の栽培、生産、製造、製作の現場はさまざまな課題を抱えていていることも多く、その現状が知られていないことさえあります。当プロジェクトでは、こうした課題の把握や解決に役立て、修理技術と用具・原材料の関係性への意識を高めるために、美術工芸品修理に必用な用具や原材料の現状を映像や画像、場合により3Dデータで記録し、公開・活用しています。
美術工芸品を未来に伝えるために ~文化財修理の技術・用具・原材料~
木、土、絹、紙、漆、金属──文化財(美術工芸品)はいずれも、自然の素材を人の手で加工し、かたちづくられたものです。そのため、時間がたてば自然に劣化します。長い時間をこえて現在まで伝えられているものは、人の手でくりかえし修理されてきた歴史があり、未来に伝えるためにはこれからも修理は必要となります。修理をする技術や、道具や材料をつくる技術など、さまざまな技術が継承されているからこそ、過去から伝えられたものを次の時代に残すことができるのです。この映像では、そうした伝統の技術をご紹介します。
文化財修理技術者 ~美術工芸品の選定保存技術~
2023年11月18~19日に京都府・みやこめっせで開催された文化庁主催イベント「日本の技フェア」で行われた、文化財の修理を行っている選定保存技術保持者たちによる座談会の様子を撮影した記録映像です。
この「1 技術者を目指したきっかけ」の他「2 仕事の緊張感や大変さ」、「3 仕事のやりがいや喜び」を公開しています。
伝統材料と道具のひみつ -彫刻刃物編-
用具・原材料の科学調査
文化財の修理・修復に使用される用具や材料については、現場での作業性をもとに洗練された使いこなしが完成していることが多く、代替が難しい場合も見られます。しかし、どのような化学組成を持ち、その物性のどの部分を活用しているかについては確認されていないことも多い状況です。必要とされる性質の由来を客観的に明らかにすることで、その素材の特性を理解し、材料の重要性の認識や代替品の可能性模索を行うことが可能になります。このような科学的な調査成果を紹介します。
調査実績等
本ウェブサイトおよび修理記録データベースの公開、用具・ 原材料の安定的な供給・使用に向けた研究等
- ノリウツギの保存方法・トロロアオイとの差異について研究、学会発表
-
椿灰(武田薬品薬用植物園よりご提供)の内容成分分析
- 装潢文化財で使用されてきた湿潤状態小麦でんぷんと、乾燥した小麦でんぷんとの比較研究
-
表装裂の伝統材料について、安定性の確認試験の実施
- 文化財修復技術者のための科学知識基礎研修(9月18日~9月20日)
- 文化財(美術工芸品)の修理記録データベースの公開(3月31日)
修理記録のアーカイブ化及び用具・材料の記録とその科学的裏付け調査等
- 装潢文化財に用いる修理用和紙の生産方法の記録と使用材料の科学的分析・今後の安定的保存方法の研究
- ノリウツギのホルマリンを使わない保存についての研究
- 彫刻・木質文化財の修理に用いる刃物の製造方法・使用方法に関する記録作成
- 株式会社小信の工房の解体先立つ3次元計測と360度動画の撮影
- 美術院による文化財修理の記録映像撮影及び聞き取り調査の編集
- 技フェアにおける技術者たちへの公開インタビュー「美術工芸品の匠」の撮影(11月18日)
- 修理技術者への実態調査等
- 各修理工房にて、現在使用している材料・用具の調査、また、今後の確保が懸念される用具・材料についての情報収集
- エントランスロビーパネル展示「文化財の修復に用いる用具・原材料の現在」(6月5日~終了しました)
用具・原材料の安定供給についての課題の調査等
- 株式会社小信での刻用刃物の撮影記録(5月23日~27日)
- 標津町における紙漉き体験会への協力と今後の研究協議(8月20日~21日、標津町生涯学習センターあすぱる)
- 修理技術者への科学的知識基礎研修(10月31日~11月2日)
- 修理技術者(特に工芸)への実態調査等
- 大西漆芸修復スタジオ(11月18日)
- 小西美術工藝社(5年1月10日)
- 目白漆芸文化財研究所(5年1月10日)
- 北村繁氏(5年1月26日)
- 活動報告
ノリウツギ・名塩和紙・本美濃紙・彫刻修理用具についての調査等
- ノリウツギ(北海道)
- ノリウツギの生産確保に関する調査
- 豊岬木材工業株式会社、北海道大学演習林、北海道・浜頓別(7 月 11 日~13 日)
- 標津町(7 月 27 日〜28 日)
- ノリウツギ保存方法に関する実験と調査
- ノリウツギの生産確保に関する調査
- 名塩和紙 (兵庫県)
- 谷徳製紙所、馬場和比古氏(11 月 19 日)
- 本美濃紙 (岐阜県)
- 美濃和紙の里会館、美濃竹和紙工房(12 月 1 日)
- 彫刻修理用具 (京都府・兵庫県)
- 美術院、竹中大工道具館(12 月 21 日〜22 日)
楮・トロロアオイ・絹・砥の粉の調査
- 9月
- トロロアオイと楮(茨城)
- 在来技法絹(長野)
- 10月
- 楮と和紙製作用具(高知)
- 11月
- 砥の粉(京都府)
ノリウツギ・トロロアオイ・五箇山和紙・石州半紙・天然砥石・大径木檜・ふすべ革の調査
- ノリウツギ(北海道)
- 北海道中頓別・浜頓別森林組合、豊岬木材工業株式会社(7月7日~8日)
- 五箇山和紙(富山県・石川県)、東中江和紙加工生産組合、石川県文化財保存修復工房(8月22日~23日)
- 石州和紙(島根県)
- 西田和紙工房、石州和紙久保田、三隅試験楮畑、酒井清美氏楮畑(9月4日~5日)
- トロロアオイ(埼玉県)
- 小川町トロロアオイ生産組合(10月15日)
- 天然砥石(京都府)
- 天然砥石館(11月18日)
- 大径木檜(長野県)
- 木曽森林管理署(11月25日)
- ふすべ革
- 中村重男商店(12月16日)
- ノリウツギ(漆箆)に関する調査
- 新潟県(2020年2月12日)
- ノリウツギの使用状況に関する調査
- 山形県(2020年3月10日~11日)
冬季に作業を行う楮、トロロアオイ、なめし革の調査
- 楮
- 高知県立追手前高等学校吾北分校(高知県吾川郡いの町)、尾崎製紙所(高知県吾川郡仁淀川町)、純信和紙工房(高知県土佐市)(2019年3月4日~6日)、高知県立紙産業技術センター(高知県吾川郡いの町)(2019年3月4日~6日)
- 那須楮生産者・相馬氏(茨城県久慈郡大子町)、東秩父村和紙の里(埼玉県秩父郡東秩父村御堂)(2019年3月10日~11日)
- トロロアオイ
- 新ひたち野農協(茨城県小美玉市)(2019年3月10日~11日)
- なめし革
- 新敏製革所・新田氏(兵庫県姫路市)、皮革史研究家・林氏(兵庫県姫路市)(2019年3月20日)
論文等
- 『保存科学』第63号(東京文化財研究所、2024)
- 西田典由・倉島玲央・長田雅裕・小林和楽・錦織正智・鈴木三男・早川典子「ノリウツギから得られたネリの黒変原因調査とその対策」
- 『月刊文化財』722号(第一法規、2023)
- 早川典子「美術工芸品の修理に用いられる接着剤の現状」
- 倉島玲央「コラム 漆芸品修理と必要な用具・原材料の現状」
- 西田典由「コラム 和紙材料「ネリ」について」
- 『月刊文化財』684号(第一法規、2020)
- 早川典子「伝統材料と技法の関連性について―科学的視点から―」
発表、講演等
- 2024年
- 粟野達也(京都大学)、西田典由、細川宗孝(近畿大学)、錦織正智(北海道立総合研究機構林業試験場)、鈴木三男(東北大学植物園)、早川典子、吉永新(京都大学)、杉山淳司(京都大学)「北海道産ノリウツギの内樹皮およびネリの特徴」第74回日本木材学会大会(京都大学)
- 西田典由、倉島玲央、長田雅弘(標津町役場)、錦織正智(北海道立総合研究機構 森林研究本部 林業試験場)、鈴木三男(東北大学)、早川典子「和紙用ネリの安定供給に向けた取り組み及びネリの各種物性に関する調査」文化財保存修復学会第45回大会(国立民族学博物館)
- 2023年
- 早川典子「文化財の修復とノリウツギ」東京文化財研究所・標津町連携協定記念講演会(標津町生涯学習センター)
修理記録データベース
文化財の修理記録には、その文化財をいつ、誰が、どのように修理・修復したかという情報が集約されています。修理記録は、作品の状態、材料、構造などにかかわる情報の次世代への継承を可能にするのみならず、文化財の管理や未来の修理にとっても重要な情報源となります。そこで当プロジェクトでは、文化財(美術工芸品)の修理記録を収集し、まずは、文化庁や独立行政法人国立文化財機構から刊行されている修理報告書をもとに「文化財(美術工芸品)の修理記録データベース」を構築いたしました。
業務実績に関する資料等(PDF)
- 報告会
- 報告書
- リーフレット
- 独立行政法人国立文化財機構 年報
- 東京文化財研究所 年報