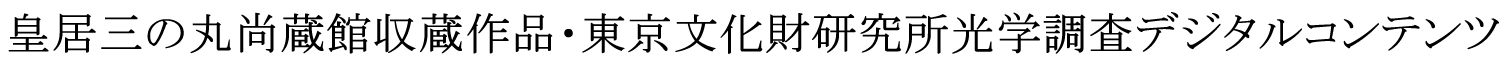雀の白い羽根(01)はCaを主成分とする胡粉で描かれている。赤色が使われている部分は少なく、画面上方の白い雀のくちばし(02)や左下方の花びらの輪郭(18)に使われているが、これらは赤色染料による着色である。落款(09)にはHgを主成分とする辰砂が使われているが、ここ以外の画面上には辰砂は使われていない。粟の実の黄色部分(10,15,24)には黄土などのFe系材料が使われている。雀の羽根などの茶色(04,05,14,22)は代赭などFe系茶色材料による着色である。茶色部分のいくつか(04,14)からは微量のPbが同時に検出された。高精細画像を詳細に確認すると、Pbが検出された部分には比較的大きな粒子径をもった橙色の粒子が点在していることが確認できる。この粒子はPb系橙色顔料(鉛丹)であると考えられるが、目視での認識は不可能である。『動植綵絵』30幅の中で鉛丹を広範囲に使用している作品は一例もなく、わずかに12「老松鸚鵡図」、17「蓮池遊魚図」において、やはり同様の使われ方が確認されたにすぎない。明緑色で描かれている葉脈(11,20)からはCuとともに少量のAsが検出されている。葉の暗緑色部分(12)にも同じ材料が少量使われているが、雀のくちばしに見られる黒緑色(08)は染料による着色である。左下方の花びらの青色(16)、黒っぽく見える岩肌(26)からはCuが検出されており、群青が使われていることがわかる。雀の目の黒色部分(03)からは比較的多くのFeが検出されており、黒漆が使われている可能性がある。(早川泰弘)
分析装置:セイコーインスツルメンツ(株)SEA200、X線管球:Ph(ロジウム)、管電圧・管電流:50kV・100μA、X線照射径:φ2mm、測定時間:1ポイント100秒、装置先端から資料までの距離:約10mm
表面
| 蛍光X線強度(cps) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 測定箇所 | 色 | カルシウム Ca-Kα |
鉄 Fe-Kα |
銅 Cu-Kα |
亜鉛 Zn-Kα |
ヒ素 As-Kα |
金 Au-Lβ |
水銀 Hg-Lβ |
鉛 Pb-Lβ |
| 01 | 白い鳥の羽根 | 白 | 98.5 | |||||||
| 02 | 白い鳥のくちばし | 薄赤 | 49.5 | |||||||
| 03 | 雀の目 | 黒 | 56.7 | 42.2 | ||||||
| 04 | 雀の羽根 | 薄茶 | 62.3 | 28.0 | 5.4 | |||||
| 05 | 雀の頭部 | 茶 | 42.0 | 22.8 | ||||||
| 06 | 目の黒剥落 下層 | 黄 | 73.1 | 19.1 | ||||||
| 07 | 雀の腹部羽根 | 黄 | 62.8 | 24.7 | 4.6 | |||||
| 08 | 雀のくちばし | 黒緑 | 64.4 | 10.7 | ||||||
| 09 | 落款 | 赤 | 32.3 | 21.8 | ||||||
| 10 | 粟 | 黄 | 154.0 | 3.9 | ||||||
| 11 | 葉脈 | 明緑 | 28.2 | 30.6 | 3.1 | |||||
| 12 | 葉 | 暗緑 | 34.8 | 39.5 | 4.9 | |||||
| 13 | 葉 | 薄緑 | 41.7 | 1.4 | 13.2 | 0.2 | ||||
| 14 | 雀の腹部羽根 | 薄茶 | 54.7 | 23.6 | 3.5 | |||||
| 15 | 粟 | 黄 | 98.6 | 7.9 | ||||||
| 16 | 花びら | 青 | 21.2 | 30.1 | 598.4 | |||||
| 17 | 花の蘂 | 黄/白 | 44.2 | 8.0 | 264.7 | 4.4 | ||||
| 18 | 青い花の輪郭 | 薄赤 | 31.0 | 12.4 | 238.6 | |||||
| 19 | 雀の腹部羽根 | 薄茶 | 70.3 | 27.7 | 3.3 | |||||
| 20 | 葉脈 | 明緑 | 6.7 | 15.7 | 630.1 | 11.8 | ||||
| 21 | 葉 | 薄緑 | 31.2 | 62.4 | 6.7 | |||||
| 22 | 雀の羽根 | 濃茶 | 46.0 | 112.6 | ||||||
| 23 | 花の蘂 | 黄/白 | 33.4 | 6.7 | 250.9 | 4.6 | ||||
| 24 | 粟 | 黄 | 84.1 | 8.3 | ||||||
| 25 | 苔 | 明緑 | 20.8 | 6.5 | 241.3 | 0.3 | ||||
| 26 | 岩肌 | 青 | 20.0 | 8.0 | 267.2 | |||||
| 27 | 絹地 | 薄茶 | 44.7 | |||||||