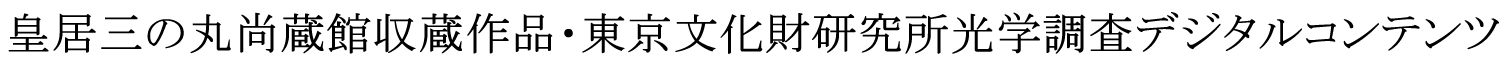白色で描かれている雪(03,04)はすべてCaを主成分とする胡粉である。灰色で描かれている降雪(05)も確認することができるが、白色の降雪部分とCa検出量はほぼ同じである。灰色に近い色調は、裏彩色として塗られている白色材料が透けて見えている部分であり、表面に白色材料が存在している部分は白色が際立ち、盛り上がりも感じられる。水面に潜る鳥の尾羽に見える白色線は一本の線のように見えるが、詳細に観察すると、白い点の集まりとして表現されていることがわかる。この作品の中では画面右上方に描かれている鳥の首部の赤色部分(01)にだけHg系赤色顔料の辰砂が使われている。鴛鴦のくちばし(16)や足(21)、さざんかの花びら(25)など他の赤色部分はすべて染料による着色である。中央上方の鳥の羽根や黒目周囲の黄色(07)に黄土などのFe系材料が使われているが、さざんかの蘂の黄色(23,24)には石黄などのAs系材料が使われている。黄色い蘂が花芯の緑色(顔料)と重なっている部分では、蘂の黄色が茶色に変色していることがわかる。鴛鴦の羽根(18)や頭部(15)に見られる緑色、さざんかの蘂や葉脈(26,28)、あるいは苔(32)などの緑色部分にはCuとともにAsが検出される緑色顔料が使われている。さざんかの葉全体に見られる深緑色(31)は緑色染料による着色である。黒っぽく見える岩肌部分(33)も詳細に観察すると青色を確認することができ、Cuを主成分とした群青の粗い粒子による着色が行われていることがわかる。画面中央上方の鳥の頭部の薄青色部分(06)から主として検出されるのはCaだけであり、胡粉が用いられていることはわかるが、青色材料の特定が難しい。可視分光測定によると有機染料の藍が使われている可能性はあるが、『動植綵絵』30幅の製作最終期に見出される青色染料とは全く異なる色調である。この薄青色は、「動植綵絵」30幅の中ではこの部分以外にはほとんど見ることのできない色調表現である。(早川泰弘)
分析装置:セイコーインスツルメンツ(株)SEA200、X線管球:Ph(ロジウム)、管電圧・管電流:50kV・100μA、X線照射径:φ2mm、測定時間:1ポイント100秒、装置先端から資料までの距離:約10mm
表面
| 蛍光X線強度(cps) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 測定箇所 | 色 | カルシウム Ca-Kα |
鉄 Fe-Kα |
銅 Cu-Kα |
亜鉛 Zn-Kα |
ヒ素 As-Kα |
金 Au-Lβ |
水銀 Hg-Lβ |
鉛 Pb-Lβ |
| 01 | 鳥の首 | 赤 | 24.3 | 27.2 | ||||||
| 02 | 鳥の羽根 | 茶 | 29.3 | 10.7 | ||||||
| 03 | 枝の雪 | 白 | 101.5 | |||||||
| 04 | 雪 | 白 | 81.6 | |||||||
| 05 | 雪(遠景) | 灰 | 96.4 | |||||||
| 06 | 鳥の頭部 | 薄青 | 58.9 | |||||||
| 07 | 鳥の目の周囲 | 黄 | 55.5 | 49.7 | ||||||
| 08 | 鳥の羽根 | 濃茶 | 27.1 | 2.5 | ||||||
| 09 | 鳥の羽根 | 茶 | 31.4 | 4.6 | ||||||
| 10 | 絹地 | 薄茶 | 30.7 | |||||||
| 11 | 落款 | 赤 | 28.4 | 15.3 | ||||||
| 12 | 鳥の羽根 | 黄 | 45.0 | |||||||
| 13 | 鳥の羽根 | 赤 | 37.8 | 0.2 | ||||||
| 14 | 鳥の目 | 黒 | 69.2 | |||||||
| 15 | 鳥の頭部 | 緑 | 16.3 | 0.2 | 329.2 | 5.3 | ||||
| 16 | 鳥のくちばし | 赤 | 65.4 | |||||||
| 17 | 鳥の羽根 | 暗青 | 23.7 | 9.8 | 208.5 | |||||
| 18 | 鳥の羽根 | 緑 | 13.1 | 1.9 | 246.1 | 5.0 | ||||
| 19 | 鳥の羽根 | 茶 | 49.0 | 12.0 | ||||||
| 20 | 鳥の羽根 | 暗赤 | 27.7 | |||||||
| 21 | 鳥の足 | 赤 | 94.2 | |||||||
| 22 | 花の中心 | 緑/白 | 69.4 | 10.6 | 571.8 | 10.5 | ||||
| 23 | 花の蘂 | 黄 | 53.7 | 2.9 | 78.1 | 464.9 | ||||
| 24 | 花の蘂 | 暗黄 | 80.1 | 5.9 | 223.7 | 218.7 | ||||
| 25 | 花びら | 赤 | 84.0 | 1.7 | ||||||
| 26 | 葉脈 | 緑 | 30.8 | 39.5 | 0.2 | |||||
| 27 | つぼみ | 緑 | 10.8 | 8.7 | 424.3 | 5.2 | ||||
| 28 | 葉脈 | 緑 | 29.7 | 5.3 | 158.4 | 2.5 | ||||
| 29 | 岩肌 | 暗青 | 21.3 | 21.0 | 617.7 | |||||
| 30 | 岩肌 | 薄灰 | 67.5 | |||||||
| 31 | 葉 | 深緑 | 32.4 | 2.0 | ||||||
| 32 | 苔 | 緑 | 21.4 | 6.4 | 270.5 | 3.7 | ||||
| 33 | 岩肌 | 暗青 | 20.9 | 7.5 | 215.9 | |||||
| 34 | 鳥の羽根 | 暗緑 | 33.3 | 70.2 | 0.2 | |||||
| 35 | 鳥の羽根 | 暗青 | 30.9 | 6.1 | 107.3 | |||||