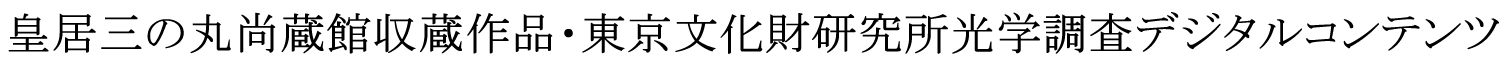梅の花や鳥の羽根に使われている白色はすべてCaを主成分とする胡粉である。赤色については、顔料による赤色は見受けられず、落款(10,11)にのみHgが検出される。赤色染料による着色が梅の花の萼(08)や鳥の目に見られる。黄色については、梅の花の蘂に見られ、目視では明るい黄色(05,12)とやや暗い黄色(04)の2種類が存在しているのを確認することができる。しかし、両部分に使われている材料に違いはなく、これらの部分から主として検出されるのはCaだけである。Caは白色材料の胡粉に由来するものであり、それに黄色染料を併用していることがわかる。梅の白い花びらに黄色染料がにじんでいる部分も観察することができる。小鳥の喉の黄色部分(02)にも黄色染料が使われている。この作品と同じように、画面全体に梅花が描かれている作品として8「梅花皓月図]があるが、梅の萼の赤色、蘂の黄色ともに本作品とは異なる材料が使われており、絵画材料という観点からは両作品の類似性は低い。木の幹(07)や洞などの茶色部分からはFeが検出される。その濃淡によってFe検出量が異なるが、材料としては代赭が使われていると考えられる。画面左下の洞部分などは表面が茶色であっても、裏彩色として黄色が存在しており、黄土が裏彩色に使われている。緑色としては、梅花の蘂、草(06)、苔などに使われており、これらの箇所からはCuとともに少量のAsが検出された。梅花の蘂の緑点は、黄色染料が重なっている部分では、ややくすんだ発色をしている。梅花中央に描かれている緑点にはその中央に濃緑色染料が置かれている。ただし、羽根を広げた小島の脇に描かれている梅花二輪だけには、この濃緑色染料が置かれていない。小鳥の羽根に使われている緑色部分(01)からはCuがまったく検出されず、緑色染料が使われている。青色は画面下方の岩肌(09)に確認できるだけであるが、Cuが大量に検出され、群青が使われていることがわかる。小鳥の黒目(03)からは少量ではあるが、Feが検出された。岩の下方には墨線による水の表現が描かれている。水の存在をこのような形で表現しているのは、30幅中でもこの部分だけである。(早川泰弘)
分析装置:セイコーインスツルメンツ(株)SEA200、X線管球:Ph(ロジウム)、管電圧・管電流:50kV・100μA、X線照射径:φ2mm、測定時間:1ポイント100秒、装置先端から資料までの距離:約10mm
表面
| 蛍光X線強度(cps) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 測定箇所 | 色 | カルシウム Ca-Kα |
鉄 Fe-Kα |
銅 Cu-Kα |
亜鉛 Zn-Kα |
ヒ素 As-Kα |
金 Au-Lβ |
水銀 Hg-Lβ |
鉛 Pb-Lβ |
| 01 | 鳥の体 | 緑 | 62.9 | 2.6 | ||||||
| 02 | 鳥の喉 | 黄 | 85.3 | 0.1 | ||||||
| 03 | 鳥の黒目 | 黒 | 55.7 | 10.1 | ||||||
| 04 | 梅花 蘂 | 黄 | 97.1 | 0.1 | ||||||
| 05 | 梅花 蘂 | 明黄 | 133.3 | 0.2 | ||||||
| 06 | 木の枝の草 | 緑 | 40.8 | 2.4 | 209.1 | 3.1 | ||||
| 07 | 木の幹 | 茶 | 58.9 | 2.8 | 51.1 | |||||
| 08 | 梅花の萼 | 赤 | 69.8 | 0.3 | ||||||
| 09 | 岩肌 | 青 | 37.0 | 8.3 | 244.9 | |||||
| 10 | 落款(角) | 赤 | 38.4 | 1.6 | 34.0 | |||||
| 11 | 落款(丸) | 赤 | 59.9 | 0.2 | 9.4 | |||||
| 12 | 梅花 蘂 | 明黄 | 90.4 | 1.7 | ||||||