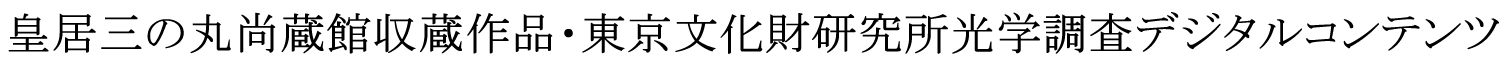白い蝶の羽根 (06) や白い花びら (20)には、すべてCaを主成分とする顔料(胡粉) が使われている。裏彩色の有無により、白色の色調が異なって見えるが、表面および裏面 に使われている白色材料はすべて胡粉である。濃赤色の花びら (15) にはHg系赤色顔料 (辰砂)が使われているが、薄赤色の花びら部分 (09) にはHg系赤色顔料は使われてお らず、赤色の有機染料による着色が行われている。画面右下の白い花の蘂は白色顔料に赤色染料が重ね塗りされているが、この部分は剥落が激しい。黄色い蝶の羽根 (08) や花の蘂(19,22) などにはCa系白色材料とともに黄色の有機染料が用いられている。左下の薄赤色の花の蘂 (19) は白色顔料に黄色材料が重ね塗りされているが、この部分では小さな気泡のような穴が多数観察される。左上方に大きく描かれている蝶の黄色い羽根 (03) からはFeが検出されており、黄土が用いられている可能性がある。下方中央に描かれている白い花の中心部の黄色い蘂部分 (21) は、下層に薄緑色材料の存在を目視で確認することができる。葉や葉脈には、薄緑色 (11) と濃緑色 (10,23) の2種類の緑色顔料の存在を確認することができる。これらの部分に使われている緑色顔料は、Cuとともに少量のAsが検出される材料である。一方、粒子感のない暗緑色・深緑色として葉 (17) や茎全体に用いられているのは有機染料である。薄緑色顔料で描かれている葉脈中心線は短い線を斜めに連続配置することで、1本の線に見えるように描き出している。16「棕櫚雄鶏図」などで同様の葉脈の描き方が見られる。青色は画面中央の黒羽根の蝶の文様 (12) や左上方の黄色い蝶の羽根文様 (01) に使われており、これらの箇所にはCu系青色顔料(群青) が使われている。蝶の羽根などに見られる灰色 (13) や黒色部分 (04,18)からはCaのみが検出されており、墨あるいは薄墨による着色であると思われる。(早川泰弘)
分析装置:セイコーインスツルメンツ(株)SEA200、X線管球:Ph(ロジウム)、管電圧・管電流:50kV・100μA、X線照射径:φ2mm、測定時間:1ポイント100秒、装置先端から資料までの距離:約10mm
表面
| 蛍光X線強度(cps) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 測定箇所 | 色 | カルシウム Ca-Kα |
鉄 Fe-Kα |
銅 Cu-Kα |
亜鉛 Zn-Kα |
ヒ素 As-Kα |
金 Au-Lβ |
水銀 Hg-Lβ |
鉛 Pb-Lβ |
| 01 | 蝶の羽根 文様 | 青 | 9.4 | 15.4 | 344.6 | |||||
| 02 | 蝶の羽根 文様 | 橙 | 20.4 | 11.2 | ||||||
| 03 | 蝶の羽根 文様 | 黄 | 43.7 | 9.7 | ||||||
| 04 | 黒蝶の羽根 | 黒 | 37.2 | |||||||
| 05 | 絹地 | 薄茶 | 26.0 | |||||||
| 06 | 白蝶の羽根 | 白 | 65.6 | |||||||
| 07 | 落款 | 赤 | 11.7 | 43.3 | ||||||
| 08 | 黄蝶の羽根 | 黄 | 21.8 | |||||||
| 09 | 芍薬の花 | 薄赤 | 28.4 | |||||||
| 10 | 芍薬の葉 | 緑 | 13.9 | 2.6 | 218.0 | 4.3 | ||||
| 11 | 葉脈 | 薄緑 | 14.0 | 4.1 | 166.4 | 3.4 | ||||
| 12 | 蝶の羽根文様 | 薄青 | 29.1 | 4.1 | 74.4 | |||||
| 13 | 白蝶の胴部 | 灰 | 87.0 | |||||||
| 14 | 花の蘂 | 黄 | 74.7 | |||||||
| 15 | 花びら | 赤 | 3.2 | 67.3 | ||||||
| 16 | 花の蘂 | 暗赤 | 29.4 | |||||||
| 17 | 葉 | 深緑 | 27.3 | |||||||
| 18 | 蝶の羽根 | 黒 | 30.8 | |||||||
| 19 | 花の蘂 | 黄 | 89.1 | |||||||
| 20 | 花びら | 白 | 72.9 | |||||||
| 21 | 花の蘂 | 暗黄/緑 | 85.4 | 4.0 | 282.6 | 6.3 | ||||
| 22 | 花の蘂 | 薄黄 | 27.7 | |||||||
| 23 | 葉 | 緑 | 20.6 | 0.1 | 194.5 | 3.0 | ||||