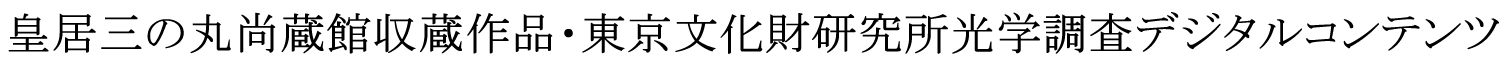白色の雄鶏の羽根(20)はCaを主成分とした胡粉によるものである。この白い羽根の部分には金(金茶)色が透けるように見えるが、他の作品と同様、この部分からAuは一切検出されない。検出されるのはCaと少量のFeだけである。黄土あるいは代赭などの裏彩色と、表面での胡粉の線描や薄塗りを用いて、このような美しい表現を描き出している。この作品中にAuはまったく使われていない。黄色としては2種類の材料が使われている。一つはFeを含む黄土で、鶏の黒目周囲(12)、くちばし(23)、足などに使われている。一方、画面左上方の棕櫚の幹に見える黄色部(05)からはFeはまったく検出されなかった。胡粉が塗られた上に、黄色染料による着色が施されている。赤色としても2種類が認められる。一つは鶏冠(10)に使われている赤色で、Hgを主成分とした辰砂である。もう一つは黒い羽根の雄鶏の黒目周囲に使われている赤色(13)で、この部分からHgはまったく検出されず、赤色染料が使われている。この作品の最大の特徴は緑色の使い方である。棕櫚の葉には明緑色の葉脈が描かれており、どの葉についても必ずCuとAsが検出されるが、葉によってCuとAsの含有量が異なっていることが明らかになった。隣り合う葉であっても、Cu>Asの葉(01)とCu<Asの葉(02)があるなど、微妙な色調の違いを描き出していたことがわかる。現在、目視でその違いを確認することは大変難しいが、若冲のこだわりを強く感じさせる作品の一つである。棕櫚の葉の葉脈は1本の線のように見えるが、細かな点を斜めに配置して遠目には1本の線に見えるように描いている部分がある。意図的にしてもあまりに精緻すぎ、すさまじいまでのこだわりが感じられる。棕櫚の葉の暗緑色部分(06)からはCuが検出されず、Asが比較的多く検出された。他の作品では、葉を描くのに使われる暗緑色は染料のみであることが多いが、この作品については描き方がやや異なっているようである。また、鶏の黒目周囲(14)や地面(22)などには緑色染料が使われている。緑色に関して、Cu、Asの含有量を変化させて色調の違いを描き出している作品は『動植綵絵』の中に2幅あり、この作品と10「芙蓉双鶏図」である。本作品中に青色の絵具は見いだされない。黒い羽根部分(19)からCaは検出されるが、Feはほとんど検出されない。(早川泰弘)
分析装置:セイコーインスツルメンツ(株)SEA200、X線管球:Ph(ロジウム)、管電圧・管電流:50kV・100μA、X線照射径:φ2mm、測定時間:1ポイント100秒、装置先端から資料までの距離:約10mm
表面
| 蛍光X線強度(cps) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 測定箇所 | 色 | カルシウム Ca-Kα |
鉄 Fe-Kα |
銅 Cu-Kα |
亜鉛 Zn-Kα |
ヒ素 As-Kα |
金 Au-Lβ |
水銀 Hg-Lβ |
鉛 Pb-Lβ |
| 01 | 棕櫚の葉 葉脈 | 明緑 | 49.7 | 23.5 | 6.6 | |||||
| 02 | 棕櫚の葉 葉脈 | 明緑 | 39.9 | 12.8 | 24.8 | |||||
| 03 | 棕櫚の葉 葉脈 | 明緑 | 46.7 | 2.8 | 52.5 | 4.3 | ||||
| 04 | 棕櫚の葉の中心 | 明緑 | 32.6 | 2.9 | 4.2 | 57.7 | ||||
| 05 | 棕櫚の幹 | 黄土 | 111.3 | |||||||
| 06 | 棕櫚の葉 | 暗緑 | 41.6 | 3.1 | 36.0 | |||||
| 07 | 棕櫚の葉の先端 | 薄緑 | 57.4 | 5.6 | ||||||
| 08 | 土坡 | 薄緑 | 57.4 | |||||||
| 09 | 草 | 明緑 | 46.3 | 2.7 | 43.4 | 1.8 | ||||
| 10 | 鶏の鶏冠 | 赤 | 4.0 | 140.4 | ||||||
| 11 | 鶏の目 | 黒 | 72.9 | 15.1 | ||||||
| 12 | 鶏の目 | 黄 | 70.7 | 14.8 | ||||||
| 13 | 鶏の目 | 赤 | 72.5 | 19.2 | ||||||
| 14 | 鶏の目 | 緑 | 57.2 | 6.7 | ||||||
| 15 | 鶏の目の周囲 | 薄赤 | 17.0 | 56.2 | ||||||
| 16 | 鶏の鶏冠の後部 | 黄 | 159.3 | |||||||
| 17 | 鶏の目の周囲 | 薄赤 | 30.6 | 29.9 | ||||||
| 18 | 鶏の首 | 薄赤 | 42.8 | 20.3 | ||||||
| 19 | 鶏の羽 | 黒 | 75.0 | 1.5 | ||||||
| 20 | 白い鶏の尾羽 | 白 | 185.7 | |||||||
| 21 | 白い鶏の尾羽 | 黄土 | 94.0 | 6.4 | ||||||
| 22 | 土坡の苔 | 緑 | 56.5 | 1.6 | ||||||
| 23 | 白い鶏のくちばし | 黄 | 145.6 | 5.3 | ||||||
| 24 | 地 | 薄緑 | 53.7 | 2.5 | ||||||
| 25 | 落款 | 赤 | 38.2 | 1.6 | 17.2 | |||||