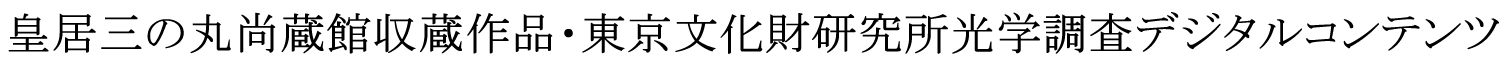鳳凰の白い羽根(15)に使われている白色材料はCaを主成分とする胡粉である。鳳凰の羽根は金(金茶)色が透けるように見えるが、この作品からAuは一切検出されていない。検出されたのはCaと少量のFeだけである。Feを主成分とする黄土あるいは代赭などの裏彩色と、表面での胡粉の丁寧な線描や薄塗りを利用した描写である。金(金茶)色が濃く描かれている頭部後方の羽根部分(23)からは、Hgも同時に検出されている。この部分では、より濃い金(金茶)色を描き出すためにHg系赤色顔料(辰砂)をわずかに併用していると考えられる。黄色い足(26)から検出された元素もCaとFeだけであるが、これらの部分では下層にCa系白色顔料が塗られ、その上に黄土などFeを主成分とした黄色顔料が着色されている。鳳凰のくちばしの付け根(20)にも黄色を確認することができるが、ここからはFeは検出されず黄色系染料が使われている。赤色部分としては、太陽(01)、鳳凰のくちばし(19)、尾羽先端のハート型赤色部(12,13,14)などが描かれているが、いずれの部分からもHgとともにPbが検出されている。Hg系赤色顔料(辰砂)にPb系橙色顏料(鉛丹)が混ぜられ、色調を変化させていると考えられる。多くの赤色部ではHgのほうがPbよりもやや多く検出されるが、桃色に見える尾羽先端のハート型赤色部の輪郭部(12)などではほぼ等量のHgとPbが検出されている。本作品と同じような太陽は11「老松白鶏図」にも描かれているが、使われている絵具は辰砂だけであり、Pbはまったく検出されていない。両作品を比較すると太陽の赤色の色調の違いを目視でも認識することができる。鳳凰の目は小さな黒点の周囲が赤茶色で塗られており(21)、この部分からはHgやPbは検出されず、大量のFeが検出された。ベンガラなどのFe系赤色材料が使われている可能性が高いが、本作品のなかでこの材料が見いだされたのはここだけである。さらに赤色材料としては、鳳凰の舌や尾羽先端のハート型赤色部の最内側の濃赤色部(14)、さらには小鳥のくちばし(10)、桐の葉の虫食い部などに赤色染料が使われている。画面上方の尾羽先端のハート型緑色部(03,04)あるいは樹木の苔(05)や葉脈(29)など緑色や明緑色に見える部分からはCuとともにAs、Znが同時に検出された。この作品で使われている緑色材料は、この顔料と松葉(11)や画面右下方の桐の葉(28)を描くために使われている緑色染料の2種類である。画面右下の花びらに見られる青色部分からはCuが検出されており、群青が使われていることがわかる。(早川泰弘)
分析装置:セイコーインスツルメンツ(株)SEA200、X線管球:Ph(ロジウム)、管電圧・管電流:50kV・100μA、X線照射径:φ2mm、測定時間:1ポイント100秒、装置先端から資料までの距離:約10mm
表面
| 蛍光X線強度(cps) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 測定箇所 | 色 | カルシウム Ca-Kα |
鉄 Fe-Kα |
銅 Cu-Kα |
亜鉛 Zn-Kα |
ヒ素 As-Kα |
金 Au-Lβ |
水銀 Hg-Lβ |
鉛 Pb-Lβ |
| 01 | 太陽 | 赤 | 4.3 | 39.6 | 57.8 | |||||
| 02 | 空 | 青 | 18.7 | 5.3 | 314.3 | |||||
| 03 | 尾羽先端 | 緑 | 12.5 | 9.1 | 675.9 | 38.7 | 18.1 | |||
| 04 | 尾羽先端 | 薄緑 | 53.8 | 7.4 | 244.8 | 22.0 | 12.9 | |||
| 05 | 苔 | 薄緑 | 10.0 | 18.4 | 329.0 | 31.6 | 12.3 | |||
| 06 | 小鳥の羽根 | 暗緑 | 27.2 | |||||||
| 07 | 小鳥の羽根 | 黄 | 39.1 | 7.9 | 8.3 | |||||
| 08 | 小鳥の足 | 黄 | 54.3 | 14.9 | ||||||
| 09 | 小鳥の目 | 黄 | 52.3 | 12.4 | ||||||
| 10 | 小鳥のくちばし | 薄赤 | 31.7 | |||||||
| 11 | 松葉 | 黒/暗緑 | 30.7 | |||||||
| 12 | 尾羽先端 | 桃 | 86.1 | 19.7 | 26.9 | |||||
| 13 | 尾羽先端 | 赤 | 24.7 | 57.2 | 27.5 | |||||
| 14 | 尾羽先端 | 暗赤 | 32.1 | 45.7 | 24.8 | |||||
| 15 | 尾羽 | 白 | 141.1 | 4.7 | ||||||
| 16 | 尾羽の骨 | 薄茶 | 33.4 | 10.6 | ||||||
| 17 | 背景 | 薄茶 | 31.6 | |||||||
| 18 | 羽根 | 薄茶 | 53.5 | 11.3 | ||||||
| 19 | 鳳凰のくちばし | 赤 | 7.6 | 63.7 | 13.6 | |||||
| 20 | 鳳凰くちばし付け根 | 黄 | 137.3 | |||||||
| 21 | 鳳凰の目 | 黒目/茶 | 47.6 | 73.6 | ||||||
| 22 | 目の中 | 薄青 | 74.8 | 2.7 | 87.6 | |||||
| 23 | 鳳凰羽根 | 茶 | 31.9 | 4.7 | 14.6 | |||||
| 24 | 鳳凰羽根 | 茶 | 49.5 | 14.7 | ||||||
| 25 | 鳳凰羽根 | 灰茶 | 113.4 | 10.3 | ||||||
| 26 | 鳳凰の足 | 暗黄 | 108.2 | 4.1 | ||||||
| 27 | 花 | 薄青 | 9.7 | 7.1 | 403.9 | |||||
| 28 | 葉 | 暗緑 | 35.3 | |||||||
| 29 | 葉脈 | 緑 | 4.3 | 29.7 | 808.5 | 81.9 | 30.7 | |||
| 30 | 幹 | 明茶 | 31.5 | 12.6 | ||||||
| 31 | 幹 | 暗茶 | 32.9 | 12.6 | ||||||
| 32 | 落款 | 赤 | 35.8 | 14.5 | ||||||
| 33 | 青い花の蘂 | 黄 | 76.4 | 5.7 | 196.9 | |||||