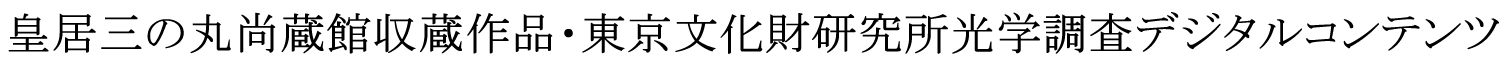白色材料としては、Caを主成分とする胡粉が使われている(09)。赤色が使われている箇所は多くないが、蝶の羽根(20)、とんぼ(03)、蛇の口(04)、いもりの身体(05)などに確認できる。これらの箇所からはHgが検出され、辰砂が使われていることがわかる。赤色染料が使われている箇所は少ないが、画面中央左のバッタの腹部などに確認できる。黄色材料としては画面左上方の蝶の羽根の黄色部分(19)からCaとともにFeが検出され、黄土などが使われていることがわかる。一方、白い花の中心に見られる黄色の蘂部分(10,11)からはFeがほとんど検出されず、黄色染料による着色であると思われる。葉先の茶色部分(15)や毛虫の目周囲の赤茶色(22)からはFeが多く検出されている。茶色の濃淡によってFe検出量に差が認められる。緑色材料としては2種類が使われている。瓢箪(02)や画面下方の岩肌の苔(06)、画面中央付近の蛙の目の周囲(08)などに使われているのは、主成分Cuに少量のAsを含む材料である。一方、粒子感のない暗緑色として描かれている葉には緑色染料が使われている。この作品中で青色は確認しにくいが、画面右中央に描かれている蛇の尻尾の先に飛んでいる虫、画面右下のトカゲ、画面左上方の蝶の羽根などに群青が使われている。蛙の黒目からは少量ではあるがFeが検出されている。画面中央の瓢箪には小さなてんとう虫が描かれ、その下方2か所に螺旋の線描がみられる。何を意味しているのか興味深い表現である。(早川泰弘)
分析装置:セイコーインスツルメンツ(株)SEA200、X線管球:Ph(ロジウム)、管電圧・管電流:50kV・100μA、X線照射径:φ2mm、測定時間:1ポイント100秒、装置先端から資料までの距離:約10mm
表面
| 蛍光X線強度(cps) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 測定箇所 | 色 | カルシウム Ca-Kα |
鉄 Fe-Kα |
銅 Cu-Kα |
亜鉛 Zn-Kα |
ヒ素 As-Kα |
金 Au-Lβ |
水銀 Hg-Lβ |
鉛 Pb-Lβ |
| 01 | 中央上の瓢箪 | 緑 | 23.6 | 14.4 | 326.3 | 4.3 | ||||
| 02 | 瓢箪の首 | 黄緑 | 19.6 | 8.6 | 330.4 | 4.9 | ||||
| 03 | とんぼの胴 | 赤 | 23.1 | 34.6 | ||||||
| 04 | 蛇の口の中 | 赤 | 53.5 | 26.3 | ||||||
| 05 | いもりの腹 | 赤 | 17.5 | 54.8 | ||||||
| 06 | 中央下方の苔 | 緑 | 5.7 | 15.0 | 661.6 | 8.7 | ||||
| 07 | 草の茎 | 明緑 | 42.2 | 5.4 | 157.5 | 1.4 | ||||
| 08 | 蛙の目の下 | 暗緑 | 50.5 | 1.1 | 47.3 | 1.4 | ||||
| 09 | 花びら | 白 | 161.3 | 1.4 | ||||||
| 10 | 花びらの中の黄点 | 黄 | 93.1 | 2.0 | ||||||
| 11 | 花びらの中の黄点 | 黄 | 141.9 | 1.0 | ||||||
| 12 | 蝸牛の殻の外側 | 紫 | 65.0 | 7.8 | ||||||
| 13 | 葉 | 緑 | 46.0 | 26.3 | 1.4 | |||||
| 14 | 葉 | 明緑 | 43.3 | 3.3 | 35.5 | 3.9 | ||||
| 15 | 葉先 | 茶 | 50.7 | 17.6 | 30.1 | |||||
| 16 | 蛙の胴 | 灰 | 68.3 | 1.6 | 4.3 | |||||
| 17 | 落款 | 赤 | 41.8 | 1.3 | 15.9 | |||||
| 18 | 芋虫の胴 | 緑 | 18.7 | 8.5 | 378.8 | 6.4 | ||||
| 19 | 蝶々の羽 | 黄 | 81.2 | 5.9 | ||||||
| 20 | 蝶々の尾 | 赤 | 41.0 | 5.4 | 12.7 | |||||
| 21 | 蛙の目 | 黒 | 40.0 | 17.9 | ||||||
| 22 | 毛虫の目の周囲 | 赤茶 | 65.5 | 48.9 | ||||||
| 23 | 地 | 薄白 | 52.9 | 1.9 | ||||||